週刊Aに連載された「街道をゆく」でSさんが、T国で見かけた犬のことを書いている。日本の植民地時代を生きた老人に飼い犬の名を尋ねると、一呼吸置き「ポチです」。これぞ日本という名ゆえに、Sさんは「言いようのない寂しさ」に沈む。
(R元総統に関する記事の書き出しが、犬の名が日本っぽいことから。それも、昔の映画のシーンの様な情景がアリアリと想像でき、寂しさに心が沈む有名作家の心情と追体験ができる)
日本の支配をくぐり抜けたT国の人たちは、それぞれに日本式の名を持つ。97歳で亡くなった元総統は「岩里政男」だった。T国で生まれ育ち、京都帝大に学び、学徒出陣で日本陸軍に入隊した人である。
(犬の名が日本っぽい話から、元総統も日本名が有り、T国人が日本人として生きざるを得なかった植民地時代を説明しつつ、元総統のプロフィールを簡潔に記述している)
終戦翌年に故郷へ戻り、40歳を過ぎてから政治の道へ。1988年、総統に登用された際は「傍流」「短命」と軽んじられた。それでも母語であるT国語を活かし、民主化に奮闘。総統の直接選挙を実現させた。
(「政治の道へ。」と文章を区切り、すぐ次の文章で「軽んじられた。」で一つの文章の様に記述するのも有りなんだ!「民主化に奮闘。」と文章を区切り、すぐ次の文章で「実現させた。」で一つの文章の様に記述する方法も有りなんだ!)
「犬が去って豚が来た」。T国でよく聞く言葉である。半世紀に及ぶ日本の支配がようやく終わったが、入れ替わるように大陸から外省人が押し寄せる。T国の本音そのものだ。
(「犬が去って豚が来た」。と一つの文章を「」で囲んだ場合、読点は外に打つんだ。「犬が去って豚が来た」は当時のT国の人々の心情を良く表している。)
総統在任中も退任後も、R氏は日本支配に対する嘆きや恨みを公言しようとはしなかった。自宅を訪れた日本人記者の目の前で、F夫人を「ふみえさん」と呼んだことも。好むと好まざるとにかかわらず、日本語をすり込まれた歳月の長さを思わせて、やはり寂しい。
(「やはり寂しい。」は、記者の心情描写である。この記事の書き出しでの「寂しさに沈む」は、S氏の心情描写で、2つが韻を踏む様になっている)
「T国の運命は自分たちT国人が決める」。苦難と屈辱に耐え、「民主先生」と呼ばれた李氏の揺るがぬ信念である。政治においても言語においても、T国とは何かを追求した稀有な哲人政治家であった。
(「と思う。」等で意見を記述せず、「稀有な哲人政治家であった。」と事実を述べる事で、記者の意見を述べつつ記事を完結する方法も有りなんだ!)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f59fc28.4449e25e.1f59fc29.a7c6f0ac/?me_id=1277822&item_id=10000816&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fnanobig%2Fcabinet%2F02988222%2Forager8%2Frobot-cleaner-r8gl3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

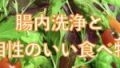
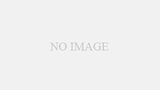
コメント