1.5/2(金)午後、I代表代行の取り計らいによりWorld Food Programme
(WFP)のColombo事務所を訪問した。スリランカ出張中の日本事務所代表:T女史とColombo事務所代表:Jeff Taft-Dick氏に面会し、I代表代行からスリランカにおけるJCCPの活動概要について説明した後、小職から地雷除去プロジェクト概要について簡単に説明した。その際、FSDがWFPに申請書(3/9付:JS-S-126添付文書)を提出しているように、WFPからJCCP地雷除去プロジェクトに資金援助できるかどうか尋ねたところ、「食糧供給に直接関係する活動以外に資金援助困難である」との回答であった。
2.5/5(月)午後、UNDPのMs. Leonie Barnesと面会し、UNDPからJCCP地雷除去プロジェクトに資金援助できるかどうか尋ねたところ、「豊富な資金源を持つDDGとの共同プロジェクトに資金援助困難であるが、スリランカのローカルNGO:Mine FreePlanetとの共同プロジェクトに対してなら資金援助可能である」との回答であった。
3.5/6(火)午後および5/8(水)午後の2回にわたり、Mine Free Planet(以下MFP)のColombo事務所を訪問し、彼らの活動内容を調査した。(添付文書 参照)
4.小職から見たMFPの特徴
(1)地雷除去チーム全員がシンハラ人で、スリランカ陸軍でEODや地雷除去を担当していた者である。
(2) 地雷除去チーム編成は、地雷除去要員10名、班長2名、通信手兼運転手2名、医療担当1名、チームリーダー1名の計16名である。(夏に1チーム、秋にもう1チーム立ち上げる予定)
(3) スリランカ空軍のEOD責任者(大佐)も軍歴20年目に退職し、MFPに参画する予定
(4) スリランカ政府(国防省)、スリランカ赤十字社、地雷ブーツの製造メーカー等が支援している。(それだけでは不十分のため外国政府に資金援助を申請している。)
(5) 地雷除去専門家を英国から招聘する。(月給5,000US$、人道的地雷除去経験12年)
(6) Administration Officerとして英国人が勤務している。(月給2,500US$、品質保証の専門家、軍経験無し)
(7) 英国でHALO Trustが英国陸軍の協力のもと立ち上がったように、MFPもスリランカ陸軍および空軍の支援のもとNGOを組織し、将来的にはイラクなどでも活動を開始することを狙っている。
5.DDG in Sri Lankaのマネージメントは下記の点で小職は不安を覚える。
(1) DDG in Sri Lankaは今年の1月から立ち上げ要員をスリランカに派遣して、活動開始の準備をしていたにもかかわらず、当初予定していた計画の詰めが甘く、計画の修正を繰り返していること
(2) 今回小職が参加したEOD訓練コースは、FSDが訓練に使用したVavuniya郊外の施設をFSDの口利きで借り、FSDのノウハウをそのまま真似して開始されたが、開始当日になっても教室の鍵が入手されていなかったり、電気の延長コード(100m)が必要なことも前日になって初めて気づいて慌てて日曜で閉店している電気店を訪問したこと (人の褌で相撲を取り自らしっかり調査や準備をしていない)
(3) EOD訓練開始を朝の7時と設定したのは良いが、ホテルのレストランなどが利用できない6時半にホテルを出発しなければならない。また、1時間の昼休みではホテルに戻って昼食を取ることは時間的に難しく、DDGの技術アドバイザーは朝食・昼食抜きで我慢していた。小職はホテル側と交渉し特別に朝6時にトーストとオムレツを朝・昼2食分準備させることに成功したから空腹では無かったが、彼らはドライバーにバナナを買いに生かせて、バナナをつまみながら授業をしていた。小職がトーストをすすめても絶対に手をつけなかった。(現場担当者は融通が利かない)
(4) 不発弾処理用の穴を掘る訓練を実施する際にも、中国製で砂をすくうのにしか使えない角スコップ1本と鍬1本で実施された。縦1m横50cm深さ1.5mの穴を掘った後、底から斜め下に横穴を与えられた道具で掘ることを要求されたが、与えられた道具では実現不可能であった。訓練終了後、小職からDDG技術アドバイザーに道具が不適正であると指摘すると、彼は逆切れして「5ヶ月、スリランカ中を捜したがこれしかない」と反論した。実際はDDGが捜していなかったようで、翌日もっと
適切な道具がVavuniyaで見つかりDDGはそれらを購入した。 (準備不足)
(5)野外訓練をするに際し、一番暑い(その時の気温、摂氏45度)11時〜14時にかけて実施するという時間設定したこと。(DDG技術アドバイザーは野外訓練中、ほとんど木陰で水を飲みながら作業を遠くから見物していた) 訓練生の一人が風邪をひいており辛そうなので小職が休むように勧めた。DDG技術アドバイザーは、訓練生の体調を気遣う様子も無かった。(安全管理・健康管理の意識が無い)
(6) 不発弾の処理訓練をすることは既に分かっていたにもかかわらず、急遽「Governmnet Agentに爆破許可申請が必要になった。」「処理する不発弾が無いからキリノッチのNPAに相談に行く」などで、訓練開始1週間目に3週間中断したこと
(7) 小職がDDGが行う講義内容に間違いや辻褄が合わない点があると指摘しても、DDG技術アドバイザーは素直に受け入れない。
(8) 医療担当者訓練コースは2週間しかなく、まったくの素人で片言の英語しか出来ない若者を集めて、通訳も付けずに医療担当者を養成していた。訓練終了後、彼らが医療担当者として勤まるとはどうしても考えられない。(FSDは医師免許を持つ人間をリクルートしている)
(9) Vavuniyaに事務所も構えず、ローカルスタッフも育てずに今に至る。ドライバーでさえ、その時々にレンタカー会社から人と車を出させて、使っている状態である。
細かい事を列挙すれば切りが無いが、今まで小職が見てきた国際地雷除去NGO:HALO Trust, MAG, NPA, FSDなどと大きく違う。
6.これらの原因として、下記のような事が考えられる。
(1) DDG技術アドバイザーは、デンマーク陸軍またはスウェーデン陸軍から短期出向する形でほとんど運営していること。(士官学校を出た将校クラスではなく高卒の一兵卒からのたたき上げ将校が人道的地雷除去活動の高給欲しさに出向していること) 一部の幹部はDDGの正規職員であるが、Programme Manager:Willadsen氏が7月中旬でDDGを退職するように、長期間に渡って海外の過酷な地雷除去現場で勤務できないようである。
(2) 要するにDDGはNGOとは名ばかりでデンマーク政府の出先機関のようなものである。(現役陸軍将校の寄せ集め組織)
(3) DDG現場担当者は、DDGの看板を背負っているという意識が低い。それほど出世が望めない「たたき上げ将校」にとって、DDGの活動は高給を貰って海外で働ける良い金儲け手段と本音では考えていると思われる。そのため、DDG本部がJCCPと訓練に関するMOUを締結しても、現場では関係なく小職などは彼らにとって単なる「厄介物」であり、スーパーバイザーに成る為の補習を受けることなどは一切期待できない。
(4) Head of DDG:Bo Bischoff氏がスリランカ訪問中、小職がMOU締結に向けてProgramme Manager:Willadsen氏と話し合っている最中、Bo Bischoff氏は一切そのことに関心が無いようであった。スリランカで何も実働プロジェクトが始まっていないためか、Bo Bischoff氏は2週間くらいスリランカ中を周って観光旅行していた模様である。組織のHeadがこのような態度では、DDGの現場マネージメントが悪くても無理はない。
7.上記のことからも2003年度中、DDG in Sri Lankaが当初の独自の地雷除去プロジェクトをしっかり運営するだけで精一杯であり、JCCPとの共同プロジェクトなど実施する余裕がないと考えられる。
8.小職からの提案
(1) 今年度の地雷除去プロジェクトは、MFPとの共同地雷除去プロジェクトを小規模(1チーム16名)で秋頃から開始するのが得策であると思料する。MFPも独力で活動を開始するのが困難な状況であり、現在協力者を捜している。スリランカ人自身の自発的な地雷除去活動開始を助ける方が本来のODAの意義に合っていると思われる。
(2) もちろん、DDGとの関係は切らずに残しておき、DDGの活動が軌道に乗る来年度以降、規模を大きくしてJCCP−DDG共同地雷除去プロジェクトを開始することを模索する。また、7月中旬からDDGが実施する地雷除去訓練コースには、小職とI氏が予定通り参加する。
(3) このような形態であれば、日本人の地雷除去専門家養成、実働地雷除去プロジェクトをスリランカで開始することの両方がどうにか無理なく実現できると思われる。(MFPとDDGの両方を上手く利用する形)

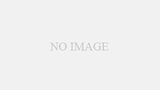
コメント